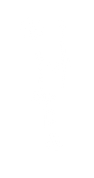
| 序 * 蘇芳香 * 秘色 * 浅葱 * 千草 * 黒鳶 * 白緑 * 青碧 * 紅樺 |
|
すぐるの母は病弱だった。藤堂の女は代々短命で、彼女もその例に漏れず、といったところだ。 藤堂宗家は分家から複数の妾をとる。内、男児二名までを、藤堂の跡継ぎ候補として迎え入れるのだ。 運良く、「二番目」にすぐるを産んだ彼女は、跡継ぎ候補の当面の乳母として藤堂本宅へ招かれるが、一年もせずに他界した。 彼女の、我が身の行く末を知っていたような儚い笑みが苦手だった。思えば東神裄燈は彼女に似ているのだ。 両親共に他界してより後、自分と兄の後見人として良くしてくれている男の面影を想う。 成人男子に対して女に似ているなどというのも失礼かもしれないが、老いを知らぬその美丈夫は、 容姿は勿論立ち居振る舞いも何処と無くしなやかだ。 薄ら寒い笑みは一体何を考えているのやら読めた例が無い。 長年顔をつき合わせているものの、彼と本音を語り合える日など、永遠に来ないのだろう、と、それだけは確かに思った。 「へぇー、すぐるんにも苦手なモンがあったわけ」 学校、屋上、フェンス、燻る紫煙。だらしなく金網に背を凭せ掛け、同じく空を見上げる少年が二人。 ぴっちりとYシャツの襟元を締めネクタイを結んでいるすぐるに対し、 隣に腰を降ろす少年は第三ボタンまでシャツを緩め派手な柄のシャツを覗かせている。 煙草を摘む指にはくすんだ銀色が幾重にも填められていた。 身形は180度違う二人だったが、 それぞれ地毛が金茶に真紅と派手な色で校内に於いて異質扱いされていた所為だろうか、妙に気が合う。 彼、雄姿(ゆうじ)は、殊更「規則」というものに反発したがる傾向があった。 制服は着崩すし、気に入りの教師の授業にしか出席しないしそれ以外の殆どの時間を屋上で潰す。 すぐるはというと、家の教育が厳しかった為か制服を着崩すのが落ち着かないだけであって 特に校則等を気にしている訳ではないので、雄姿の態度を周りが云う程奇天烈だとは思わなかった。 屋上へ続く扉の南京錠をこじ開ける彼を見ても注意すらしない。 それどころか時折一緒になってその境界線を潜り暫く空を眺めて過ごす (というと酷く青春めいた雰囲気だが実際は単にぼうっとしているだけである)。 そうして二人がお互いの顔と名前を覚えてから約一年と半、高校入学から丁度二年目。それが今日だった。 「……何だよその"すぐるん"って……」 「すぐるで止めるのって中途半端じゃない?」 「だからってわざわざ字数を増やすなよ。……まあ、別に構いやしないが」 「ならこれからはそう呼ぶよ」 にたりと笑って口元を覆う。中指と薬指の間に挟んだ煙草を咥えられる位置。妙に小慣れた呑み方をする男だ。 すぐるは吐き出される紫煙の行く先を目で追った。 「苦手か……そうだな。苦手だな」 唐突に自分で濁した話題を進める。何となく、この男になら話しても良い様な気がした。 「怖いの?」 雄姿も気にせず言葉を返す。 「……怖い。否、彼自身は怖くはない」 「何が怖いの」 ふうと息をついて一拍置いた。そのまま意味深な沈黙が降りる。 こういった不自然な間は珍しいことではなかった。 すぐるはすらすら喋る割に話の先のことをよく考えていないことが多い。 人と話していても、時折言葉を捜してぼうっとするので、しばしば、寡黙な人だと勘違いされる。 実際、この十七年間、すぐるをお喋りだなどとのたまったのは雄姿ただひとり。 その彼は、常より長いすぐるの沈黙にも辛抱強く黙っていた。 雄姿は、見かけによらず、人の話を聞くのが妙に巧い。 口の重い相手を待つゆとりと、絶妙の相槌のタイミングを心得ているのだ。 しっかりしているようで斑っ気のあるすぐるの話にちゃんとついて来れるのは、 この男と裄燈、そして幼い頃から半身のようにして過ごす瑠璃若だけである。 「――腹の内が読めないんだ。敵なのか味方なのか分からない」 「……餓鬼みたいな判別するね。敵か味方かって」 「藤堂にはそれしか居ないからな」 藤堂の一族は規模こそ大きいものの、宗家が力で捻じ伏せる中央政権である。 年に一度の総会でも宗家は分家に声どころか顔すら見せない。 代理人である裄燈が宗家の席に座り、石榴と槐が述べる。 藤堂頭首は外からも内からも命を狙われている「的」だったからだ。 ある事件を境に表立って敵意を露にする身内は減ったものの、燻っている火は決して途絶えていない。 現にすぐるは藤堂本宅から一歩出れば常に敵意の視線に晒されている。 今日まで無事であったのは単に裄燈の「護衛」があるからだろう。 「面倒見てくれて、護ってくれて、味方なんじゃねえの?」 「……それが分からないから、困ってるんだよ」 分からない。判らない。そう、行動で判ずるならば決して裄燈は敵ではない。しかし、動機が。動機が無いのだ。 以前のすぐるは例え苦手な人物であっても彼を味方と認識し頼っていた。 だが今は裄燈が「藤堂の味方と成り得ない」動機を知ってしまっている。 味方である筈が無い。なのに味方でしかない。だから彼が一層理解出来ない。 「理由は知らねぇけどさー、そいつ極度のお人よしなんじゃないの?」 「それは否定しておく。そんな生温い人ではないな」 「おっかねえんじゃん、それ」 「怖くは無い」 「俺も判んねえよその人―」 深い溜息が重なった。判らないことが身近に腐るほどある。 そんなに己は未熟なのか。 すぐるはもう一度天を仰いだ。 彼は苦手だ。はっきり云って好ましい人物と思えない。胡散臭すぎる。 しかし、好きになれないのと同様、嫌いにもなれないのは何故だ。 「若人よ、悩み苦しめそれが青春だ」 「何処の親父だよお前は」 今日は帰りに東神の家へ寄ろう。そして少しだけ、彼と話そう。 すぐるはそう決めて勢いよく立ち上がった。 同時に雄姿が煙草をコンクリートに押し付けて笑った。 最後に見上げたのは雲ひとつ無い空だった。 千草色の壁が広がる。 |