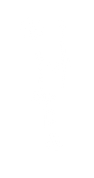
| 序 * 蘇芳香 * 秘色 * 浅葱 * 千草 * 黒鳶 * 白緑 * 青碧 * 紅樺 |
|
篝火の照らす湿った大地に、己の足元からじわじわと闇が侵食してゆく。 そのスピードは、祭壇の置かれた此処が周囲より盛り上がっている所為か、滑らかに早い。 儀式の所為で荒ぶった息を整える頃には、彼の異様に白い肌も、白銀の髪も、広がり続ける陰にどっぷりと浸かってしまっていた。 どんなに打ち消そうとしても、後悔の念がぎゅうとすぐるの心の臓を掴んだ。 間違っていない。 ―― 間違ってなどいない。 もう一度深呼吸をして、赤黒く染まった刀を祭壇へ戻した。変化は無い。 嫌な予感が当たった。ゆっくり後ろを振り向くと、彼は青白い顔を少しだけ傾けて空(くう)を見つめていた。 何の感情も読み取れない瞳は、何時見ても、言い得ぬ罪悪感を覚える。すぐるは、幼い頃から彼が苦手だった。 「すまない」 知らず搾り出したように掠れた声は、無心に自らの血の流れを追う彼に届いただろうか。 落ち着かなければ、と思う程、気持ちは逸るばかりだ。 失敗してしまった。もう、手元に策は残っていない。 どうすれば。 「気になさらないで下さい」 固く引き結んでいた唇が緩み、ほうと息が漏れた。 つい先程、もうこの声を聞くことはなくなるのだ、と覚悟したばかりだというのに。 嬉しいのか、悲しいのか、もうすぐるには分からなかった。 微動だにしない彼を抱き起こそうとして少し屈むと、ぷんと鉄錆の匂いが鼻をつく。 幾度嗅ごうとも、これには慣れることが出来ない。 ――今更ながら、ひとを斬ったのだという事実に指先が震えた。 「起きれるか?手当てをしないと」 気まずさを埋めるように、彼から目を背け、端に避けていた鞄を手に取り早口に喋った。 中には清水と布、薬と包帯、そして札(ふだ)が入っている。 「必要ありません。傷も直ぐに塞がります」 言う通り、彼が倒れこんだ直後はこちらが焦る程に溢れていた血は既に止まり、背に赤黒い一文字が刻まれていた。 しかし、それでも未だ相当痛い筈だ。 清水で湿らせた布で血を拭き取ってやりながら、不覚にも涙が出そうになった。 痛いと詰られない方が、辛い。心配気にこちらを窺う視線に気付いて表情を引き締める。 ひとの心配をしている場合じゃないだろう、裄燈。 「薬を塗る。じっとしてろよ」 「そんなことをせずとも平気です」 「良いから。言うことを聞いてくれ」 出合った当初から、彼 ―― 東神裄燈(しのみゆきとも)は自分自身をないがしろに―否、 自分に対して全く興味が無いようだった。それはすごく怖いことだ、と幼いながらに思ったものだ。 簡単に応急手当のみ済ますと、ほぼ空になった鞄はそのままに、怪我人を肩に抱え上げる。 加害者は自分だ。己にも裄燈にも色々と特殊な事情がある為、病院は無理にしろ、家まで送り届けるのが筋というものだろう。 東神邸は、この祠から藤堂家の裏庭を通ればすぐ。人目につくことも無い。 一人納得して歩を進めるすぐるの背中で、裄燈が僅かに抵抗を示した。 異常な程の回復力はあっても、痛みは常人と等しく受ける。 動くなと窘めると、観念したのか、肩にかかる重みが安定した。 「、で下さい」 「何?裄燈、今何と言っ……」 掠れた声は、背に当たるだけで、すぐるの耳には届かなかった。 そのまま意識を失ってしまった裄燈を抱え、先程よりも慎重に歩く。 すぅすぅと聞こえる寝息の、緊張感の無さに苦笑した。 ふと、後ろの、既に虚空へ溶け込んでしまった祭壇を振り返る。藤堂家の宝刀の放つ光だけがぼんやりと見て取れた。 ―― なあ、裄燈。俺たちは、間に合うだろうか。 ―― 許して欲しいのではない。罪を無かったことにしたいのではない。ただ、今からでも、 自分への言い訳に過ぎない思いに気付いて、再び苦笑し歩み始めた。 暫くして祠の入り口へ辿り着くと、外は夜明けだった。 木々の合間から覗く空は、先程まで居た世界とは比べ物にならない程の美しさで、けれど同じ色だ。 ―― 血を思わせる緋。 長い、永い一日の始まりである。 |