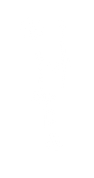
| 序 * 蘇芳香 * 秘色 * 浅葱 * 千草 * 黒鳶 * 白緑 * 青碧 * 紅樺 |
|
じわりと鳥肌の立つような空気の中、僕と「それ」はいつまでも蹲っていた。 墨染めの空間 ふたつの距離は決して短くなかった筈なのに、互いの息遣いまでも生々しく耳に届く。 「それ」はいつも泣いていたし、僕は何時また僕に襲い掛かってくるか分からない 「それ」を常に警戒していたからかもしれない。 格子越しに遠くで揺れている橙の「ひ」だけが此処で眼にする光で、 あれが誰かの手によってこちらへ近づかない限り、僕は自分の肌の色すら知ることが出来ない。 事実、僕は最期の最後まで「それ」の肌や髪、目の色が自分とそっくり同じであることを知らなかった。 むしろ知りたくも無かったのだけれど。 其の頃 僕は、ただ生きていた。 真っ黒い壁に囲まれて、世界にふたつっきりで、ただ、ただ生きていた。 あの人が眩いほどのひかりを与えてくれるまで。 「ゆきさん、ゆきさん。見てください。僕がつくったのです」 裄燈が玄関の戸を開けば間も無く、小さな足音が近づいてきた。次いで森江の慌てた声。 履物を揃え脱いで待っていると、現れたのは、細い金髪に碧の眼をした少年。大事そうに箱を掲げている。 「ゆきさん、おかえりなさい。今日はごはんまだですか。一緒に食べましょう。ゆきさんのお好きな甘味もよういしたのです」 裄燈は、足元を細々と動く少年を微笑ましい気持ちで見下ろした。 一通り報告を終えて満足するのを待ち、ふわり、頭を撫でる。 ただいま、と告げると、何度目かのおかえりなさい、が返ってきた。 遅れて顔を出した森江が、坊、頼んますから手を洗うてください、と告げる。 少年の手も、それに抱えられた箱も、餡でべたべたと汚れていた。 京都と滋賀を行き来する裄燈は、奉公先である藤堂の敷地内にも屋敷を持っている。 一年の大半は京都に詰めるが、時折、休みをとって滋賀の本宅へと帰る。手土産はいつも和菓子だ。 こどもへの土産としては半端でない量を持ち帰るのだが、大抵、裄燈と森江も加わった三人で平らげてしまう。 いつだったか、少年が、そんなにお腹がすいているのですか、と尋ねると、甘いものは好きです、と笑った。 少年にとって、裄燈が初めて見せた笑顔だった。少年は、彼の照れたような笑い方が大好きになった。 「うん、美味しい。はじめは何でも上手に作れるんですねえ」 大の男がにこにことおはぎを鷲掴んで食べる様は、今思うと何とも言い難いものがある。 だが当時の少年にとって、それだけが拠り所であった。照れ臭そうに身を捩って森江を振り返る。 森江もまた、嬉しそうに目を細めて少年を見遣る。 此処は、少年の為の箱庭だった。 |